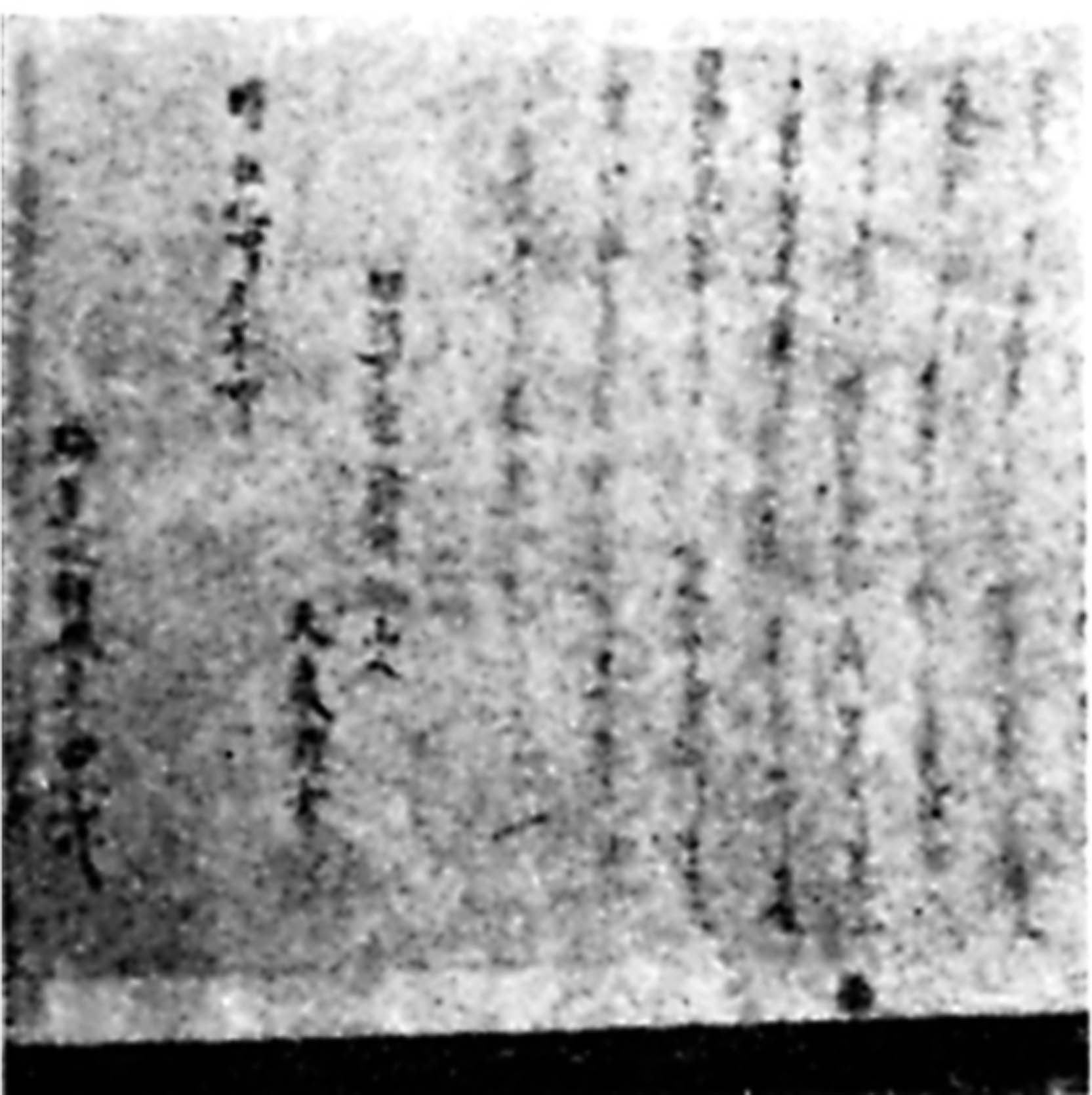善 福 寺 −山鹿字柏原
|
75 善 福 寺 −山鹿字柏原 洞山入口阿弥陀ケ池の碑の所にあったのだが、昭和三十一年(一九五六)七月道路拡張のため、現在の場所に新築移転した。無量山と号し浄土宗鎮西派芦屋光明寺末といわれている。本尊は阿弥陀如来(立像)寺内に阿弥陀堂がある。柏原区の大部分はこの寺の壇徒であって、創立年代は貞治元年(一三六二)といわれている。 ◎河 童 縁 起 書 (伝説) 寛永十七年(一六四〇)六月十五日の夜、山鹿柏原の博大濱中伊右衛門は、うまやから牛をひき出そうとしていた一匹のカッパを見つけ、大手籠で打ち伏せ捕えようとしたら、急に胸苦しくなった。一心に善福寺の本尊阿弥陀如来を念じながらやっとカッパを捕えることができたので、うまやに縛り上げておいた。その夜、伊右衛門の夢枕にカッパがあらわれ「われは多年河中にすむカッパである、一命を助けたまえば一つの功徳を立て申さん」と言うので、伊右衛門は「善福寺の阿弥陀如来の前で浦人には一切害をしないと誓え」と申しわたした。カッパはすぐ「阿弥陀如来のいますかぎり、また氏神のみやまのあらんかぎり、氏子の一人にたいしても一切手出しばつかまつらず」という誓文を書いたので、伊右衛門はカッパをはなしてやった。伊右衛門はカッパの誓紙を善福寺にとどけて事の成り行きを話した。善福寺では誓文に縁起書を書きそえ、本堂の蓮台の下に納めた。この誓文を寛政元年(一七八九)善福寺の欽随という僧が取り出して写したら、たちまち両眼が失明したといゝ伝えられている。その後弘化四年(一八四七)に書きかえた河童縁起書が、現在善福寺に保存されている。善福寺の本尊阿弥陀仏は、もとの善福寺の近くにあった井戸(俗に阿弥陀ケ池という)に沈められてあった仏像である。(芦屋町誌) ◎門 柱 − 明治三十一年(一八九八)十一月 武田源助 ◎百 度 石、− 世話人中 ◎濱 中 伊 右 衛 門 の 墓−明治十九年(一八八六) 表に圓譽浄覺居士とある。伊右衛門は寛永十八年(一六四一)四月に没しているが、その墓も朽ちばてたので山鹿村の里人達は伊右衛門のことを追懐し明治十九年(一八八六)にこの墓標を建立した。 柏原浦周施人 梶田 勘次郎 田中 幸平 田中 伊八 田中 兵作 井上 仁平 ◎そう 盤− 明治八年(一八七五)三月 林 濡三郎 中西 長平 波多野善五郎 花田 文二郎 石橋 新兵衛 ◎本 堂 − ◎大 師 堂 − 大願寺所属であったが、昭和十七年(一九四二)善福寺に移管す。 島郷四国第五十七番札所 本尊 弘法大師 ◎木 祠 − 右側の坐像は立江地蔵、左側の立像は延命地蔵である。堂山と柏原浦の闇は昭和五十二年(一九七七)に埋め立てゝ現在は陸続きになっているが、その以前は橋が掛っていた。大正初期までは橋も無く孤島であったので、堂山にある延命地蔵にじかにはお参りが出来なかった。堂山と海を暇てた柏原浦の善福寺境内に、この身代わり延命地蔵を安置して里人はお参りをした。この延命地蔵にお参りをするとお乳がよく出るようになるというので衆人の信仰をあつめている。 ※こゝの石段を上るとかなりの広さで、諸々の石造物が安置してある。こゝは昔より善福寺の飛び地境内で現在善福寺本堂のあるあたりに、小さな庵があり尼僧がこの庵のお守をしていた由、その尼僧達の墓が三体石段を上ると左側にある。 ◎弘 法 大 師 坐 像−文化五年(一八〇八)初安居日 金高山三角寺 豫州奥院 小田彦蔵 ◎八 十 八 体 の 仏 像 − ◎生 目 八 幡 宮 − 眼病の神として霊験あらたかなのでお参りも数多い。 ◎鳥 居 − 大正九年(一九二〇)十月 田中 □ 川原 悟□ 縄田 幸平 若松市 占部弥九郎 妻□□ この鳥居の柱前面に歌が刻み込まれているが、石が解(と)けていて歌詞の判読が困難である。 照す生目の水かがみ 末の世までも 曇らざりけり と詠まれている由、智田礼仙住職は語る。 ◎石 祠 − ◎修 業 大 師 像 (弘法大師等身大立像)− 行脚修業中の弘法大師像で足には草鞋をはいている。 (この広場の中央に) ◎五 重 層 塔 (一字一石望塔)− 明治十六年(一八八三)九月 発 起 多賀谷 小作 中西 藤兵衛 林 清三郎 小田 彦七郎 平橋 利吉 石工 江崎才七善秋 山鹿柏原世話人 縄田 清三郎 重岡 卯作 瓜生 藤三郎 発 起 縄田 勘次郎 田中 勘助 佐野 傅次郎 亀津 利平 この五重層塔は禅寿寺の五重層塔に次ぐ立派なものである。 ◎弘 法 大 師 坐 像 (南無大師遍照金剛) − 文化元年(一八〇四)三月 柏原浦 妙海尼謹建 石工 赤間関 口本吉兵衛 (八十八体仏像の北側中間に) ◎阿 弥 陀 如 来 坐 像 − 文久□年九月 鞍手郡野面村 吉武清右ヱ門 |